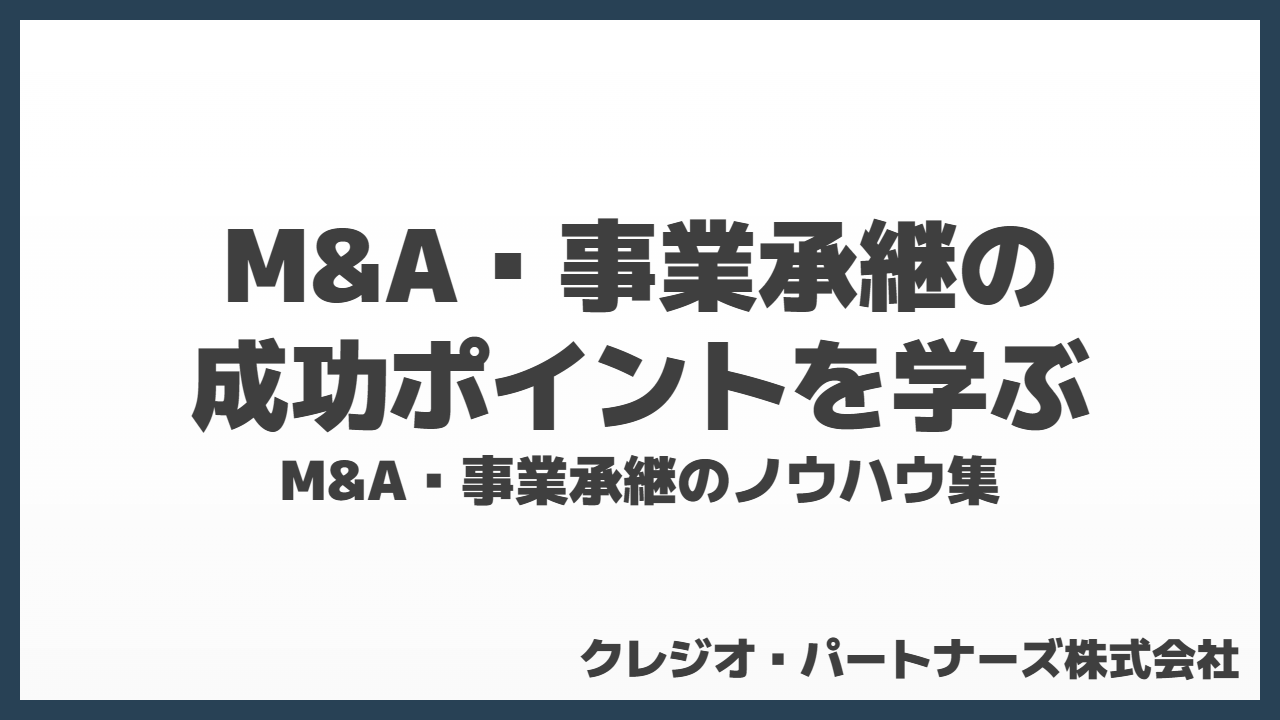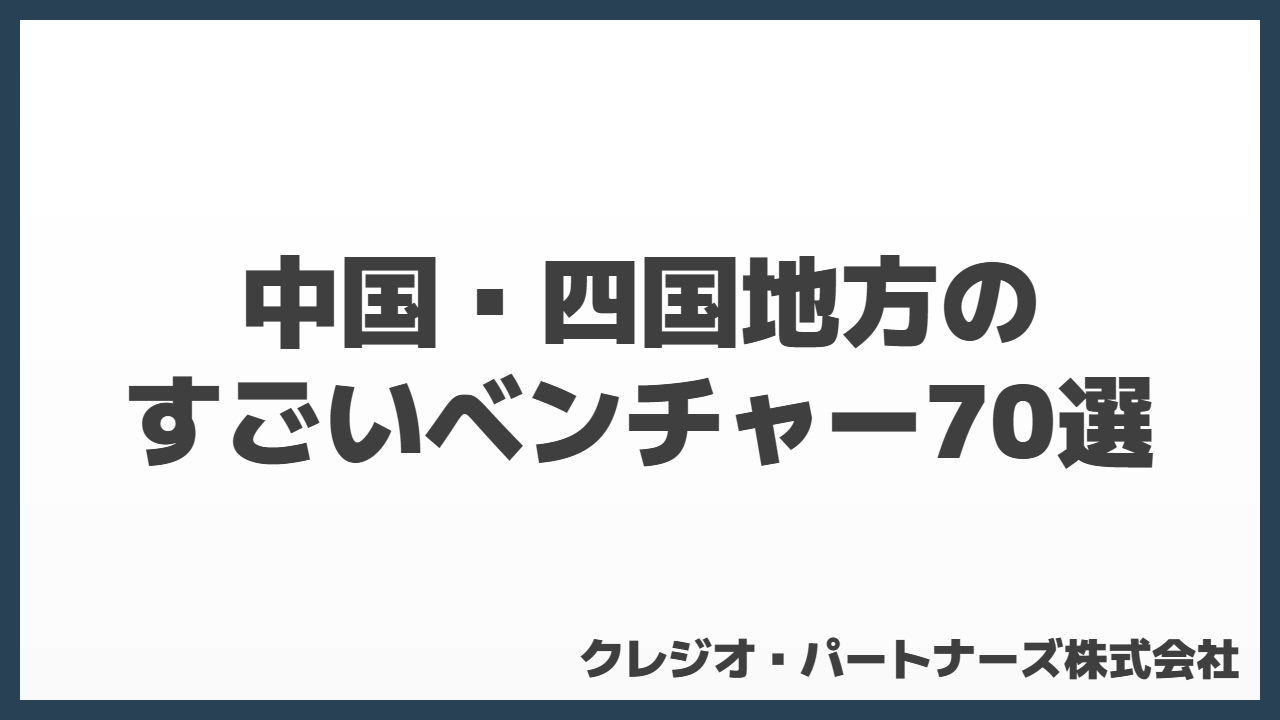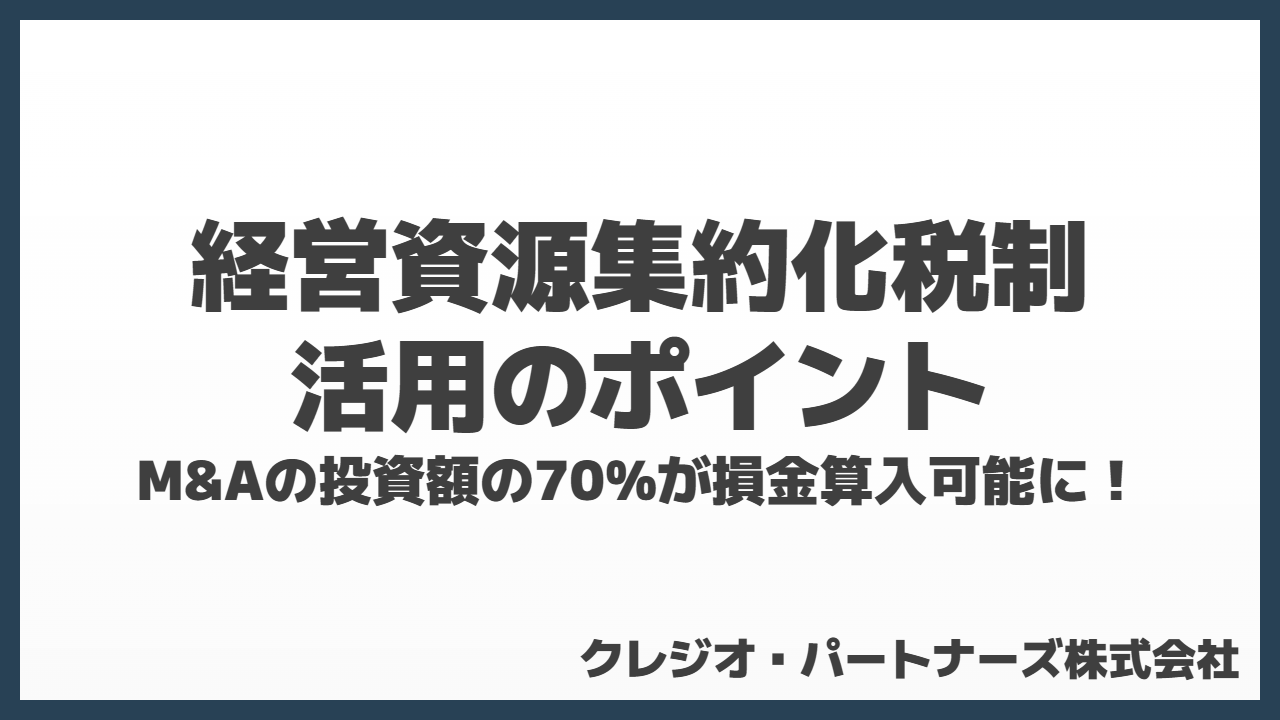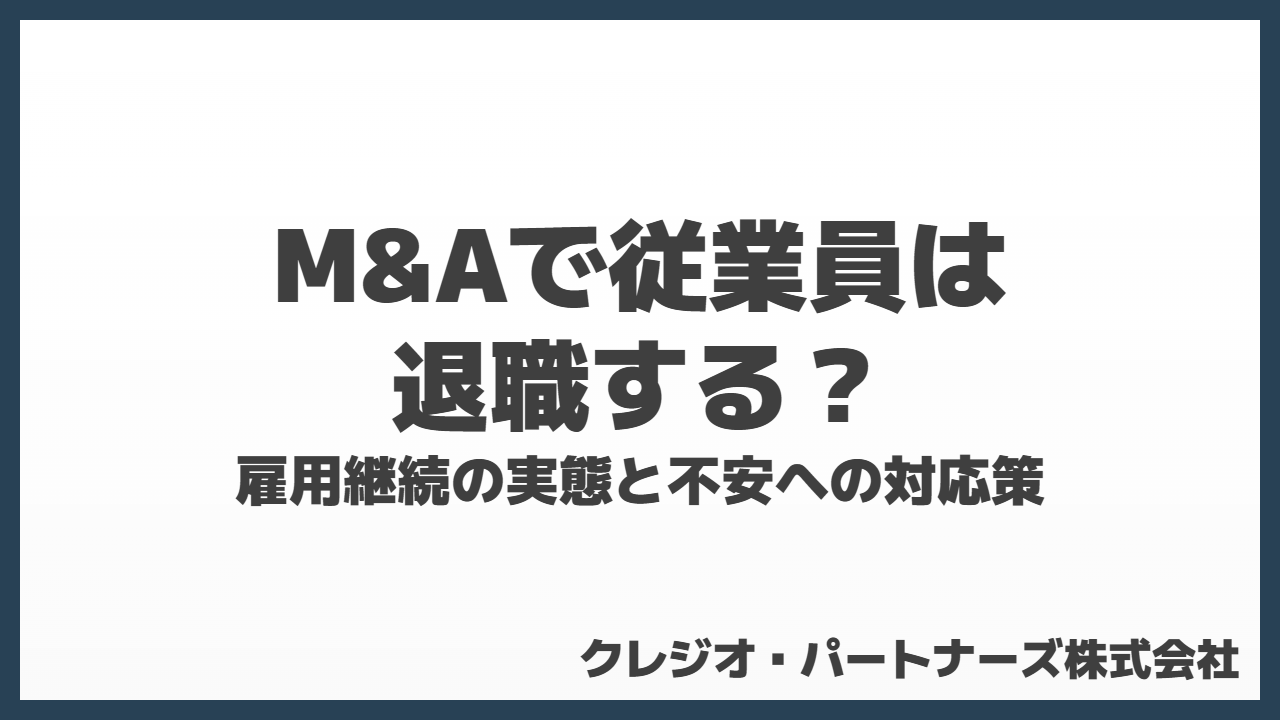55歳から始める事業承継ガイド|親族内承継・MBO・M&Aまで徹底解説
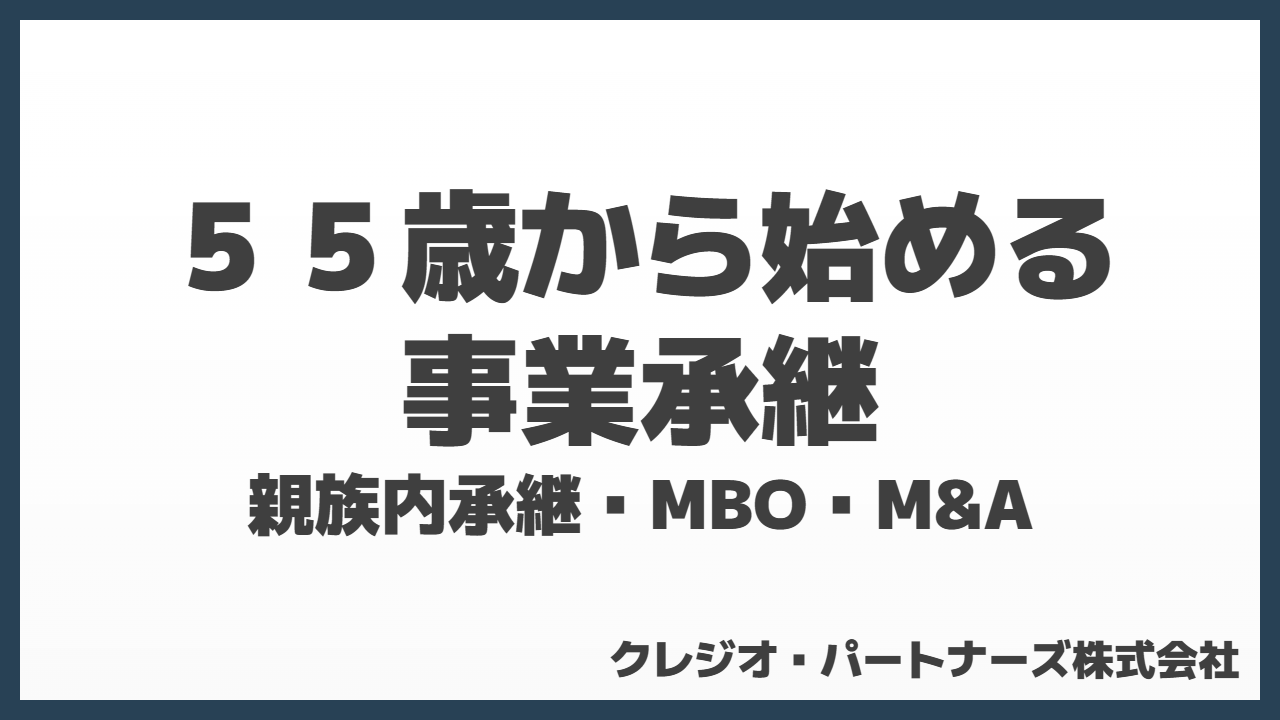
経営者の平均年齢は60歳に迫り、高齢化は全国的な課題となっています。しかし、「いつ、どのタイミングで事業承継の準備を進めればよいのか分からない」と迷う方も多いのが現実です。
事業承継は会社経営に必ず訪れる重要な局面。本記事では、55歳を目安に始めるべき理由と、承継の選択肢・進め方をわかりやすくまとめました。
目次
なぜ55歳から事業承継準備を始めるべきか
帝国データバンクの統計によると、全国の経営者の平均年齢は59.9歳となっており、経営者の年齢層が高齢化していることが指摘されています。一般的に事業承継の検討には時間を要します。
決断したからと言って、すぐに承継できるというものでもなく、関係者との調整や、税務・財務的な手続き等も含めると、事業承継の方向性を決定してからでも数年を要するのが事業承継です。事業承継は、検討・実行・承継してからのフォローまで含めると長い時間が必要なため、この期間を乗り越えるだけの体力・気力が必要です。
「一生涯を経営者で終える」と既に決定している経営者は別ですが、事業承継はあらゆる経営者にとって、どのような結果であれ、必ず来る未来です。筆者の主観で理想を申し上げると、65歳までには社長職を交代し会長職になることが理想です。
事業承継における検討・意思決定・実行・フォローといった一連の流れを実行するためには、単純な手続きのみで引き継げばよいというものではなく、経営者自身の健康・気力・意思決定力等を考えると、55歳という年齢から検討を始めること重要です。
その年齢であれば、一度方向性を決めて、上手くいかなかったとしても、別の方向性を検討することができます。そのため、55歳~60歳までには、事業承継に向き合う機会が必要です。
参考:帝国データバンク「全国社長年齢分析(2020年)」
55歳から考える事業承継の選択肢
親族内承継の検討
事業承継を考える場合、まず最初の手段として、自身の息子・娘や、兄弟・親戚など親族への承継を考える必要があります。一般的に日本はファミリー企業が多いことで有名です。
様々な事業承継のケースを見ても、「自分の子供に継いで欲しい」という想いは、経営者の誰しもが考える選択肢であり、この選択肢の可能性を検討し、結論を出しておく必要があります。
親族内承継を検討する際には2つポイントがあります。
経営者適性の判断と育成期間の確保
一つ目は、後継者候補となる親族の「経営者の適性」です。
経営者の適性は一朝一夕で身につくものではありません。経営そのものの経験の有無や、従業員・取引先との関係性等、自社の事業について特にマネジメントの部分で適正があるかを判断する必要があります。
親族内承継を選択する多くの経営者は、早いタイミングで、後継者候補を自社に呼び戻す等して、経営に早くから関わらせていることが多いです。このように経営者適性を判断し、育成するための十分な期間が確保できるのが親族内承継の特徴です。
相続税・贈与税への対策と専門家相談の重要性
二つ目は、相続税・贈与税の検討です。
会社の株式や資産を引き継ぐ場合、相続税・贈与税を納める必要があります。自社の業績・株価に応じて相続税・贈与税の額は変わります。こちらは、事業承継に詳しい税理士等の専門家にどのような対策があるかを事前に相談しておくことが必要となります。
特に、上記一つめのポイントで一番大事なことは「親子間のコミュニケーション」です。
父親と息子が、対等な立場で、会社の事業承継について率直に意見交換できるというケースは稀です。地域企業の場合、「息子は地域外(東京・大阪等)へ行ってしまった」という場合が多く、経営に忙しい社長は、家族とのコミュニケーションを母親に任せがちです。
母親を介したコミュニケーションだけでは、事業承継の深い話をすることは難しいです。55歳という年齢になると、残された期間は後10年程度であることを強く意識し、早めに子供と向き合うことが必要となります。
従業員承継(MBO)の検討
もう一つの大きな手段は、従業員(役員含む)へ引継ぐことです。
上記の親族内承継と同じく、「経営者の適性」を判断する必要があります。従業員への承継においても、経営者としての育成期間は必要です。もし親族があまり経営に関わってこなかったという場合、普段から業務に従事している役員や従業員への承継は、比較的現実的な選択肢のように思えます。
従業員承継の場合、注意すべきポイントは、上記の「社長就任」の意思と、「自社株買い取り」の意思と資金力があるかです。事業を引き継ぐ場合、その会社の株式を買い取ることとなります。
株式を買い取るためには資金が必要であり、後継者候補はこの資金を準備する必要があります。金融機関でも、従業員承継向けの融資メニューは存在していますが、個人で借金を抱えてでも、その会社を引き継ぐという強い意思が必要となります。
関連記事:MBOとは?従業員承継のメリット・デメリットと活用スキームを解説
株式は別の者が所有し、経営者は別の者が行うという、いわゆる「所有と経営の分離」という方法や、ファンドを活用する等の方法もありますが、それぞれメリット・デメリットもあり、従業員承継はなかなか思うように進まないというのが現状です。
小規模な企業の場合、従業員の経営者育成にチャレンジしてみたが、難しかったという結論を出されている方も多いように見受けます。
関連記事:事業承継3つの方法とは?親族内承継・MBO・M&Aと所有と経営の分離を解説
得意先への事業引継ぎ
事業を引き継ぐ選択肢の一つに、得意先への事業引継ぎがあります。このケースは、特に取引先の依存度が一社に集中している場合に起こりやすいケースです。
取引先として、自社のビジネスの業界や、事業に詳しく、相手先の経営者が信頼できる経営者であれば、現実的な選択肢であるように思えます。
事業引継ぎ後を考えても、事業面でのシナジー効果を検討しやすい一方で、これまでの関係性もあり、交渉面ではなかなか本音が言いづらい等のケースもありますが、事業引継ぎの有力な選択肢となります。
関連記事:取引先・得意先とのM&Aは可能?事業承継のメリット・デメリットと注意点
第三者承継(M&A)
M&Aは第三者に会社の事業を引き継ぐことを指します。上記の「得意先への事業引継ぎ」も手法としては、M&Aの手法を用いることとなります。得意先以外の候補も含めて、第三者へ事業を引き継ぐという選択肢もあります。
第三者に事業を引き継ぐことは、「自社事業の継続」「買手との相乗効果(シナジー効果)による事業成長」「雇用の継続」「取引先・仕入先との取引継続」「オーナー家株主に株式譲渡代金が入る」等のメリットがあります。
ここで必要なのは、事業承継の選択肢の中で、「M&A」も選択肢の一つに考えておくということです。M&A以外の選択肢も様々なメリットがあります。全ての選択肢を比較考量する中で、M&Aについてもその中の一つに入れておくことが重要であると考えます。
関連記事:M&Aによる事業承継とは?第三者に事業を引き継ぐメリットを解説
事業承継を成功させる総合判断のポイント
これまで4つのステップを示しましたが、これらは必ずしも順番である必要はありません。情報の取扱いに十分注意した上で、様々な選択肢の可能性を検討し、総合的に判断していく必要があります。
事業承継は多種多様であり、経営者だけではなく、親族・株主・取引先・従業員等、様々な関係者が絡みますので、正解はありません。加えて、事業承継までの期間も長くなるため、「なんのために事業承継するのか」という目的をきちんと定めておくことが必要です。
目的の中には、「事業を継続すること」「従業員の雇用を継続すること」等の事業面もあれば、「なるべく高く株式を売却する」といった株式オーナーとしてのメリットを追求する場合や、「自分の親族に継がせたい」等、ファミリーとしての側面もあります。
自分自身として、どの方向性で事業承継を進めたいかの検討を進める中で、目的を固め、意思決定をした上で、具体的な取組に行動していくことが必要です。円滑に進めるためには、55歳くらいから検討を進めていくことをおススメします。
関連記事:事業承継3つの方法とは?フローチャートでわかる親族内承継・MBO・M&A
まとめ|55歳からの準備で円滑な事業承継を実現
事業承継はすべての経営者に必ず訪れる未来です。55歳から準備を始めることで、親族内承継・従業員承継(MBO)・M&Aなど、幅広い選択肢を比較検討しながら、最適な方法を選ぶ時間的余裕を持つことができます。
しかし、実際には税務・法務・金融・人材育成など多くの課題が絡み合い、経営者一人で判断するのは容易ではありません。だからこそ、早めに専門家へ相談し、第三者の視点を取り入れることが重要です。
私たちも地域企業の事業承継やM&A支援に豊富な実績を持っています。事業承継の準備に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。信頼できるパートナーと共に進めることで、円滑で後悔のない事業承継を実現できます。
クレジオ・パートナーズ株式会社広島を拠点に、中国・四国地方を中心とした地域企業のM&A・事業承継を専門に支援しています。資本政策や企業再編のアドバイザリーにも強みを持ち、地域金融機関や専門家と連携しながら、中小企業の持続的な成長をサポート。補助金や制度活用の知見を活かし、経営者に寄り添った実務的な支援を提供しています。
URL :https://cregio.jp/
M&A・事業承継について、
お気軽にご相談ください。