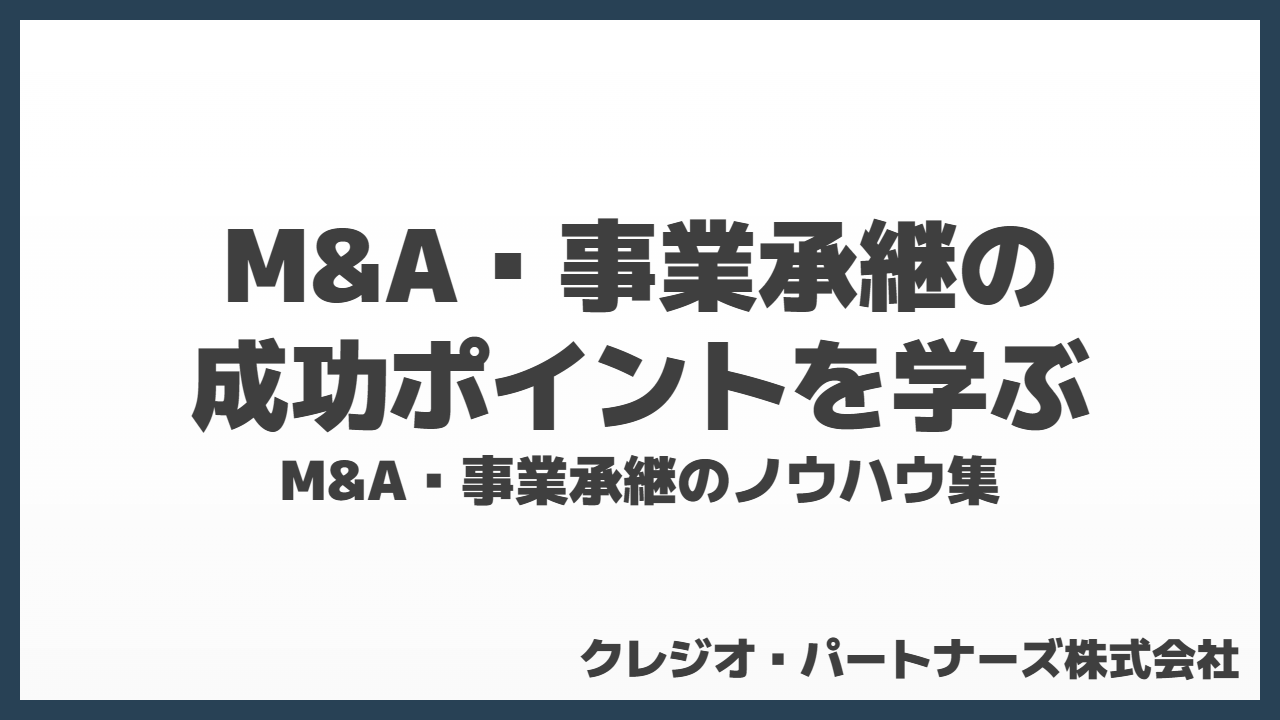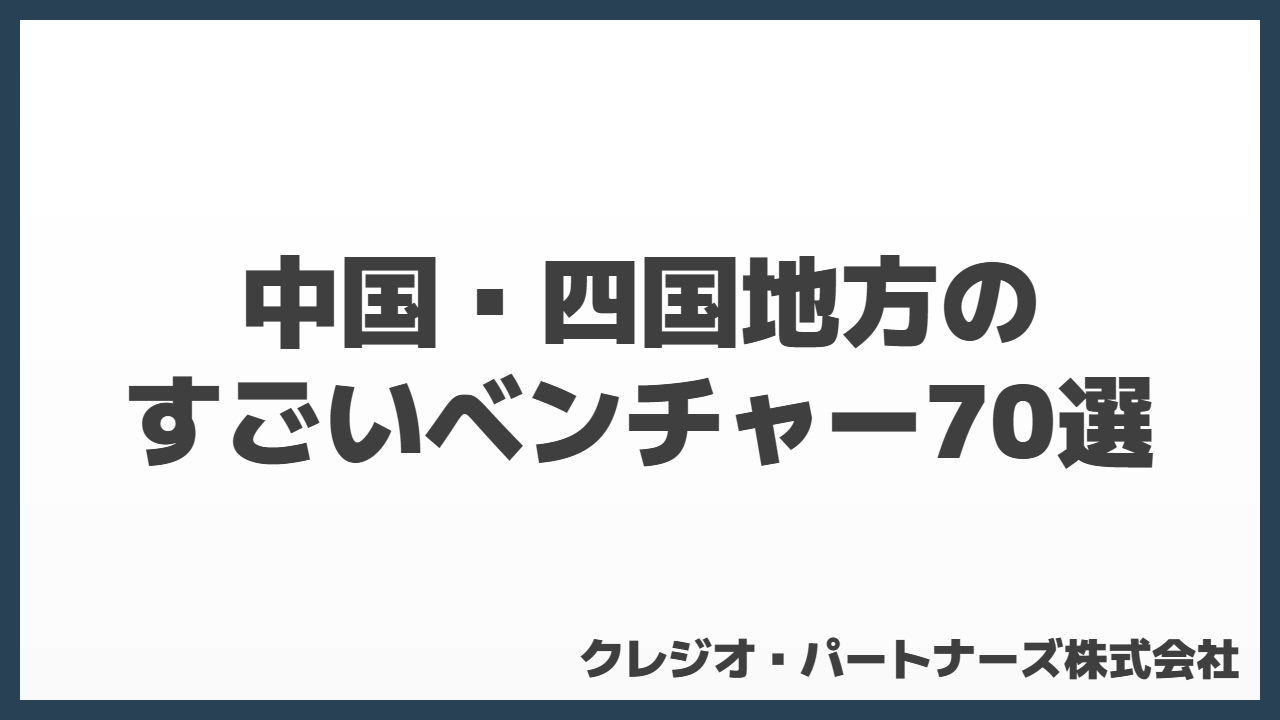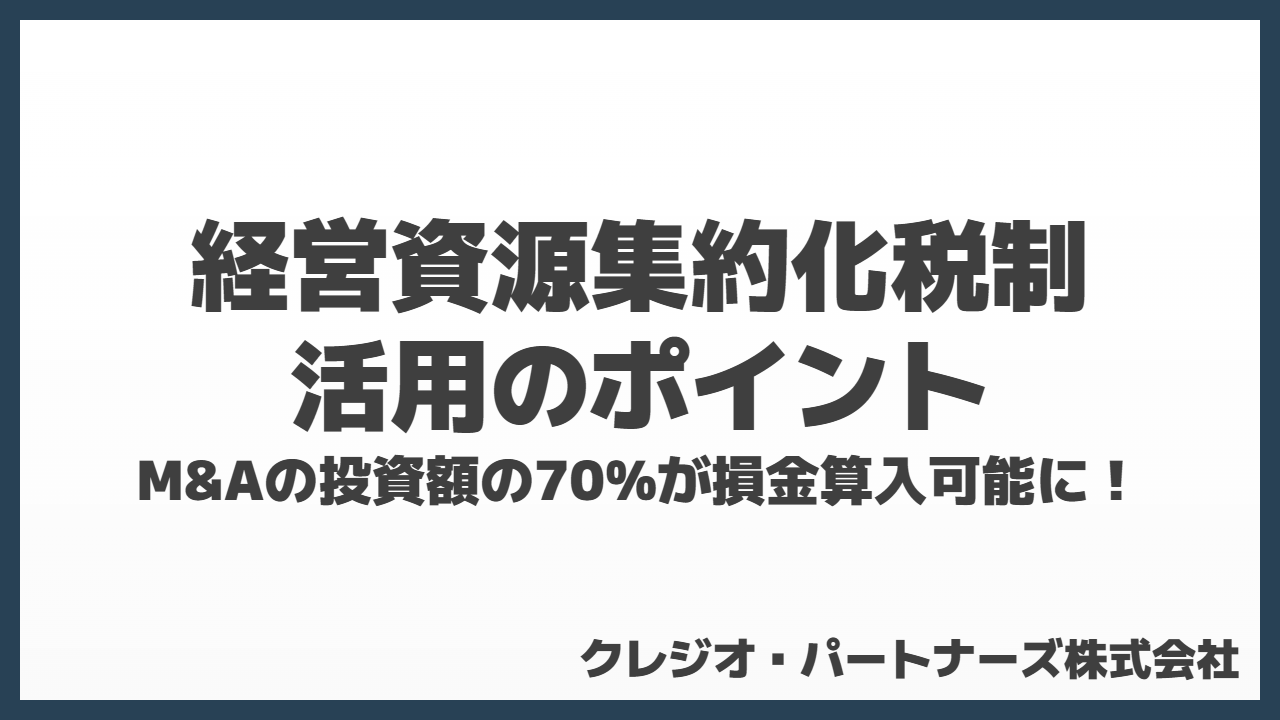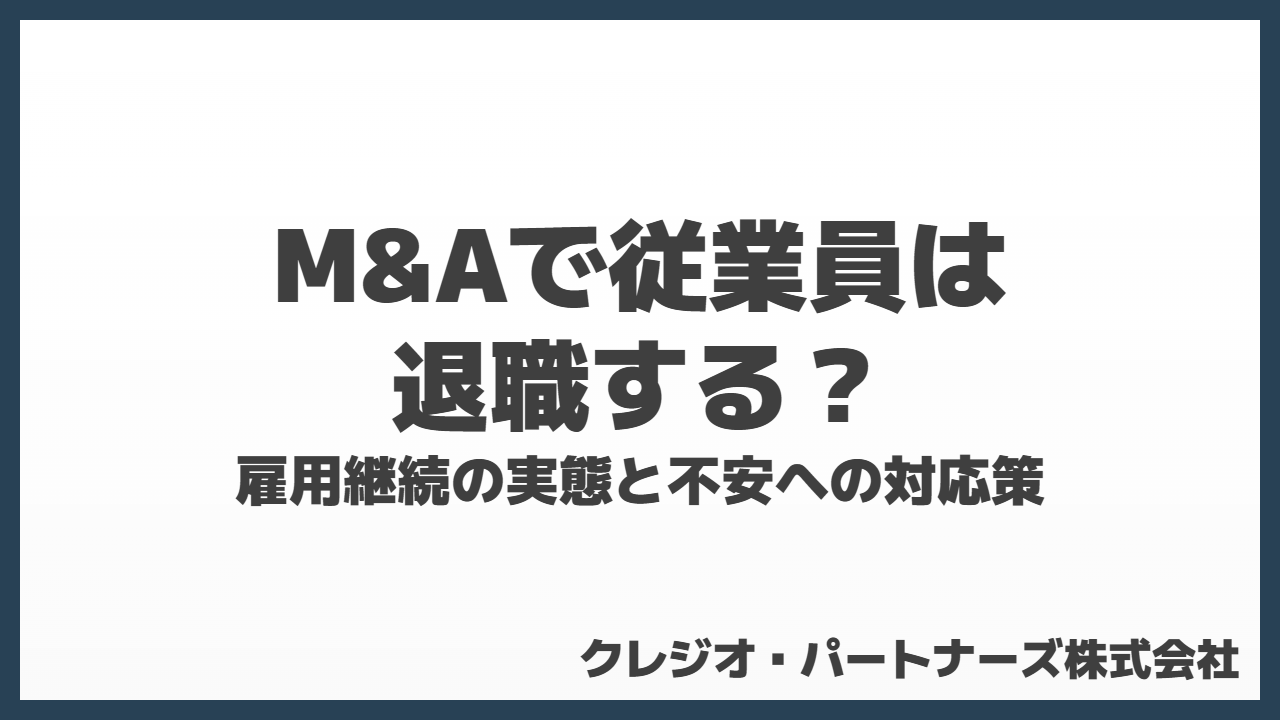補助金は返さなくていい?収益納付と返還義務の仕組みを徹底解説!
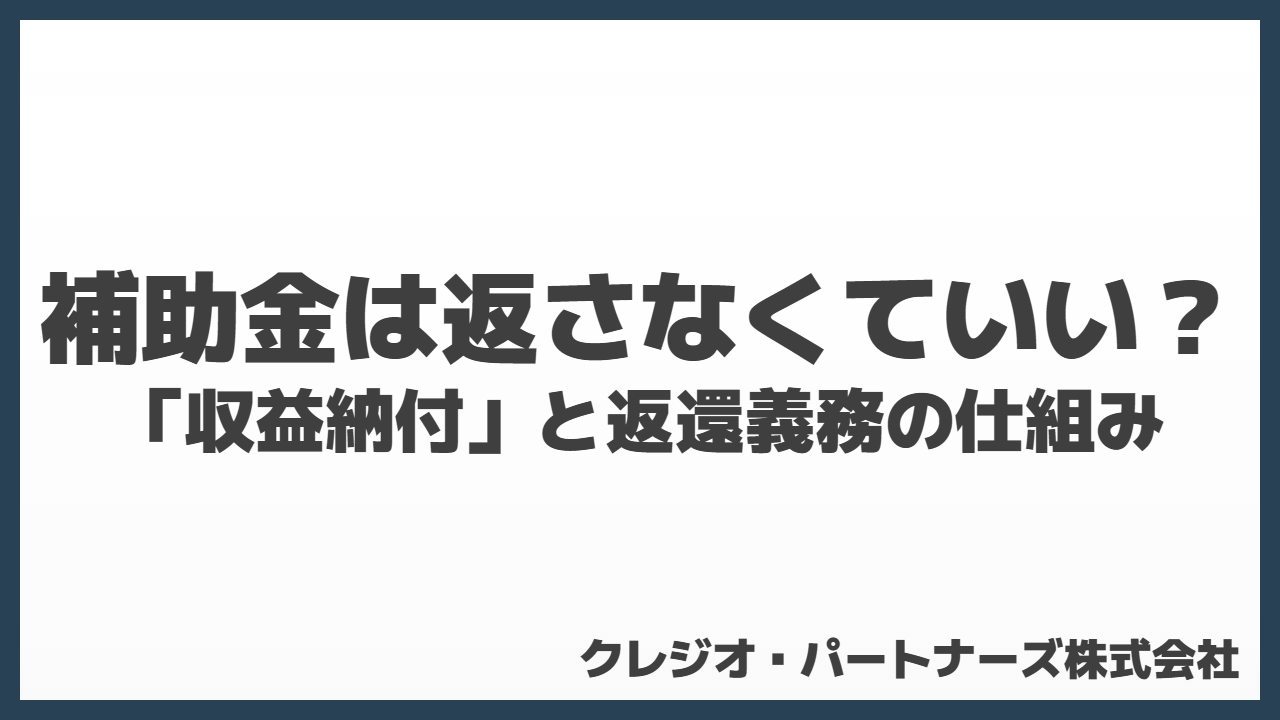
「補助金は返さなくていい」とよく言われますが、実際には返さなければならないケースも存在します。補助金は融資のように返済を前提としない制度ですが「収益納付」と呼ばれる仕組みによって、補助金の活用で得た収益が一定以上となった場合には、国に返納(返還)を求められることがあるのです。
本記事では、補助金における「返さなくていい」という一般的な認識の誤解を解き、収益納付の仕組みや返還が発生する具体的な条件、免除規定の有無などをわかりやすく解説します。「補助金は本当に返さなくていいの?」と疑問に感じている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
記事のポイント
- 補助金には「収益納付」という考え方が存在。
- 具体的な条件は補助金制度ごとに公募要領で定められている。
- 除外や免除等、弾力的な運用をしている補助金制度も存在。
「収益納付」とは?
補助金にも法律があり、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下、適化法)」という法律において、各省庁の補助金は法律の規定に準ずることになります。同法第七条二項において、以下の条項が設けられています。
(適化法第七条二項)
第七条
2 各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。
簡単にお伝えすると、各省庁は「相当の収益が生ずると認められる場合」において、「補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる」と記載されています。
こちらに記載している「相当の収益」が何を意味するか等の具体的な条件にあたる部分については、それぞれの補助金の公募要領において記載されているケースが多いです。
また、「条件を附することができる」の記載から分かるように、全ての補助金において、収益納付義務が課される訳ではありません。ただし、補助事業を実施することにより、収益性が見込まれる事業については、こういった収益納付義務が課される場合が多いです。
公募要領で見てみる「収益納付」
具体的な公募要領では、収益納付がどのように記載されているかを例示で確認してみます。
令和2年度補正予算小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の場合
【参考6】収益納付について
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります(これを「収益納付」と言います)。
本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。なお、ここで言う「補助金により直接生じた収益」は、以下のようなケースを想定しています。
<補助金により直接収益が生じる(⇒交付すべき補助金から減額する)ケースの例>
- (1)補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益(機械装置等費等が補助対象の場合)
- (2)補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(広報費が補助対象の場合)
- (3)補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合)
- (4)補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)
- (5)販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入(借料等が補助対象の場合)
上にあるケースのような補助事業を行う場合は、「(様式4)小規模事業者持続化補助金交付申請書」にある「5.補助事業に関して生ずる収入金に関する事項」は「あり」と回答のうえ、収入金に関する事項として「参加者から徴収する参加費収入」、「展示販売会での販売による利益」等と簡潔にご記入ください。
なお、「商品の生産やサービスの提供に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラシの作成や配布」、「ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)」、「広告の掲載」、「店舗改装」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここでいう「補助金により直接生じた収益」には該当しないと考えます。
また、「設備処分費」の支出は、廃棄または所有者への返還を前提とした経費支出のため、「補助金により直接生じた収益」には該当しません。
参考:令和2年度補正予算日本商工会議所小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>公募要領 第7版
令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領〔一般型・グローバル展開型〕の場合
(4)事業化状況の報告から、本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として収益納付しなければなりません(事業化状況等報告の該当年度の決算が赤字の場合や十分な賃上げ(年率平均3%以上給与支給総額を増加させた場合や最低賃金を16地域別最低賃金+90円以上の水準にした場合等)によって公益に相当程度貢献した場合は免除されます)。
(参考)令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領〔一般型・グローバル展開型〕公募要領
上記のとおり、いずれの補助金も補助金交付額を限度に収益分を返納する「収益納付」について規定されています。前者の持続化補助金の場合、収益の定義を「事業完了時までに直接生じた収益金」と定義しています。
それに対して、後者のものづくり補助金については、「本事業の成果の事業化又は知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合」と定義されており、事業完了の時期を超えて、補助事業の成果による収益を指しており、違いがあります。
なお、前者の持続化補助金では、「商品の生産やサービスの提供に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラシの作成や配布」、「ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)」、「広告の掲載」、「店舗改装」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないことを理由に収益の定義から外しています。
後者のものづくり補助金においても、「決算が赤字の場合」や「十分な賃上げを増加させた場合」に免除規定を設けており、弾力的な運用になっています。
収益の状況を確認する「事業化状況報告」
上記のものづくり補助金のような事業の成果による収益を対象とした場合、収益の状況を確認するため「事業化状況報告」という報告書の提出義務が課されます。
「事業完了日が属する会計年度の終了後5年間について事業化状況を報告することとなります。補助事業終了後もこういった事務的コストが発生することについて留意が必要です。
《公募要領抜粋》
(3)本事業の完了した日の属する会計年度(国の会計年度である4月~3月)の終了後5年間、毎会計年度終了後60日以内に本補助事業に係る事業化等の状況を事業化状況(収益状況含む)・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。
(参考)令和元年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領〔一般型・グローバル展開型〕公募要領
まとめ
今回は「補助金は返さなくていいのか?」という疑問に対して、収益納付という法律上の仕組みと、公募要領での具体的な扱いについて解説しました。
事例として紹介した「小規模事業者持続化補助金」や「ものづくり補助金」では、収益が発生した場合に返納を求める一方で、赤字や賃上げなど公益性が高い取り組みを行った場合は免除されるなど、柔軟な運用が行われています。
つまり、「補助金はもらったら返さなくていい」という一面的な理解ではなく、制度ごとに収益納付の有無や条件を確認することが重要です。申請前に公募要領をよく読み、返還義務の有無を理解したうえで、自社に合った補助金制度を選ぶことが、賢く補助金を活用する第一歩と言えるでしょう。
クレジオ・パートナーズ株式会社広島を拠点に、中国・四国地方を中心とした地域企業のM&A・事業承継を専門に支援しています。資本政策や企業再編のアドバイザリーにも強みを持ち、地域金融機関や専門家と連携しながら、中小企業の持続的な成長をサポート。補助金や制度活用の知見を活かし、経営者に寄り添った実務的な支援を提供しています。
URL :https://cregio.jp/
M&A・事業承継について、
お気軽にご相談ください。