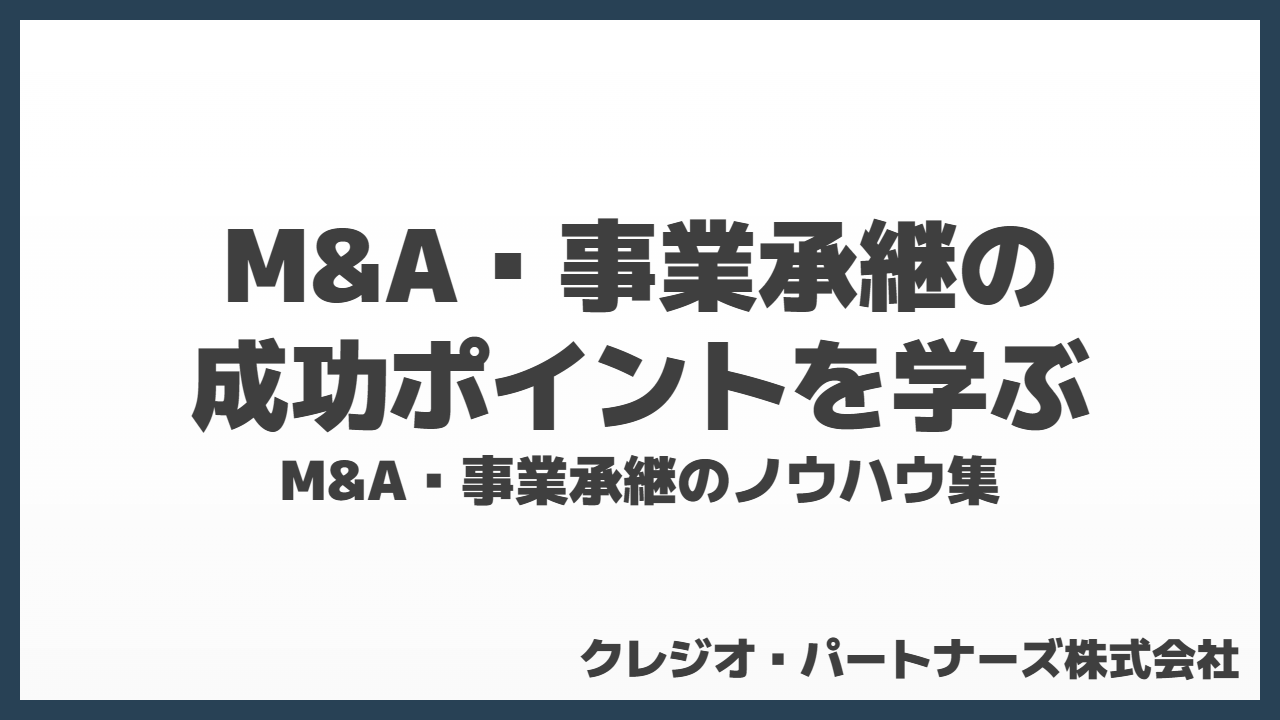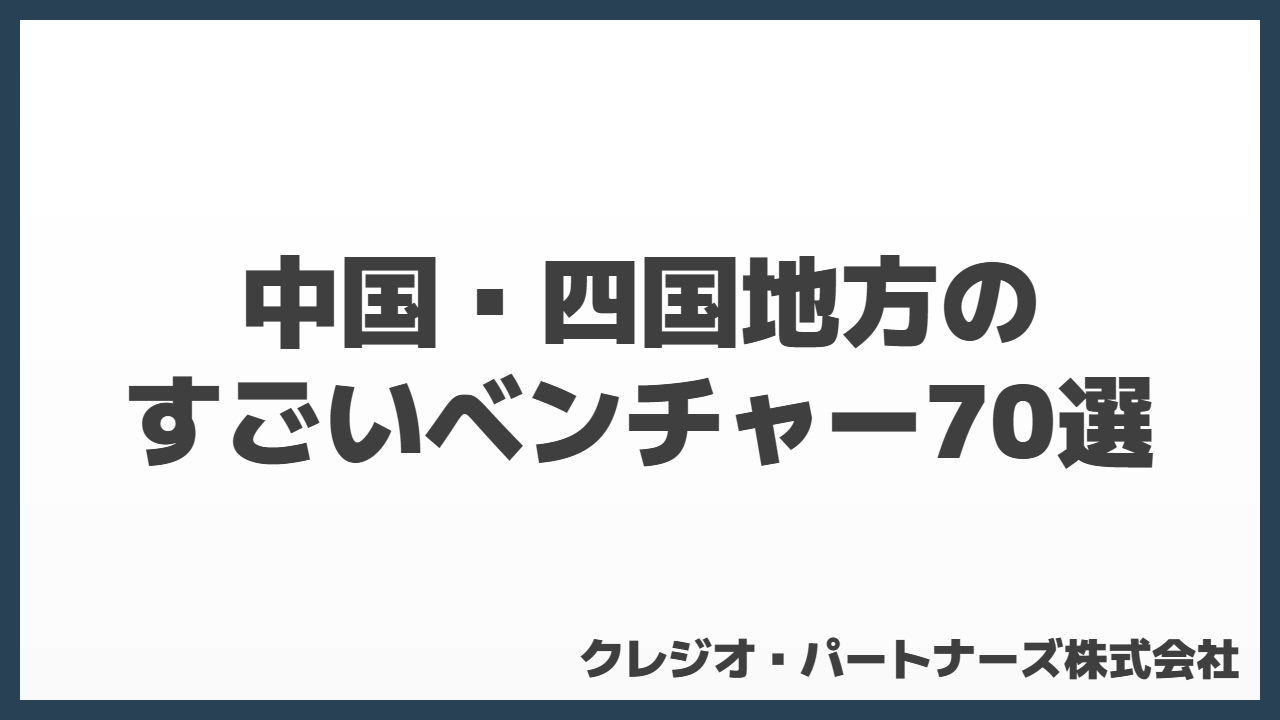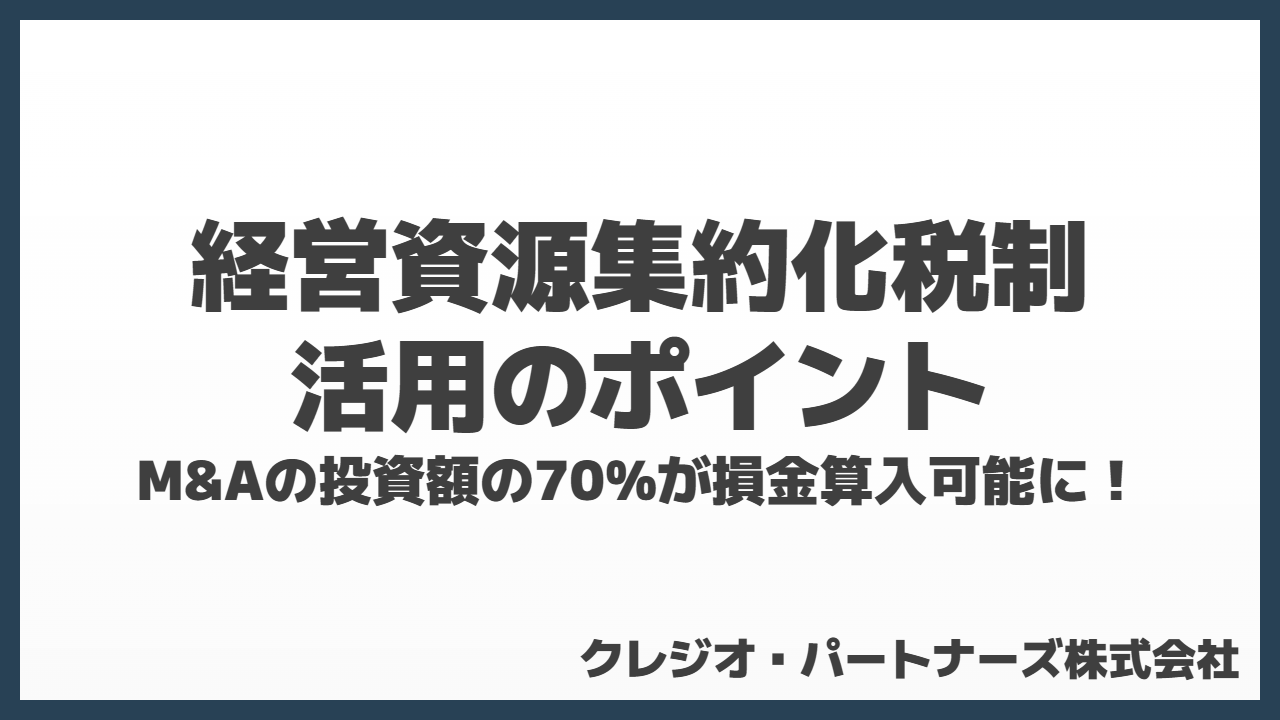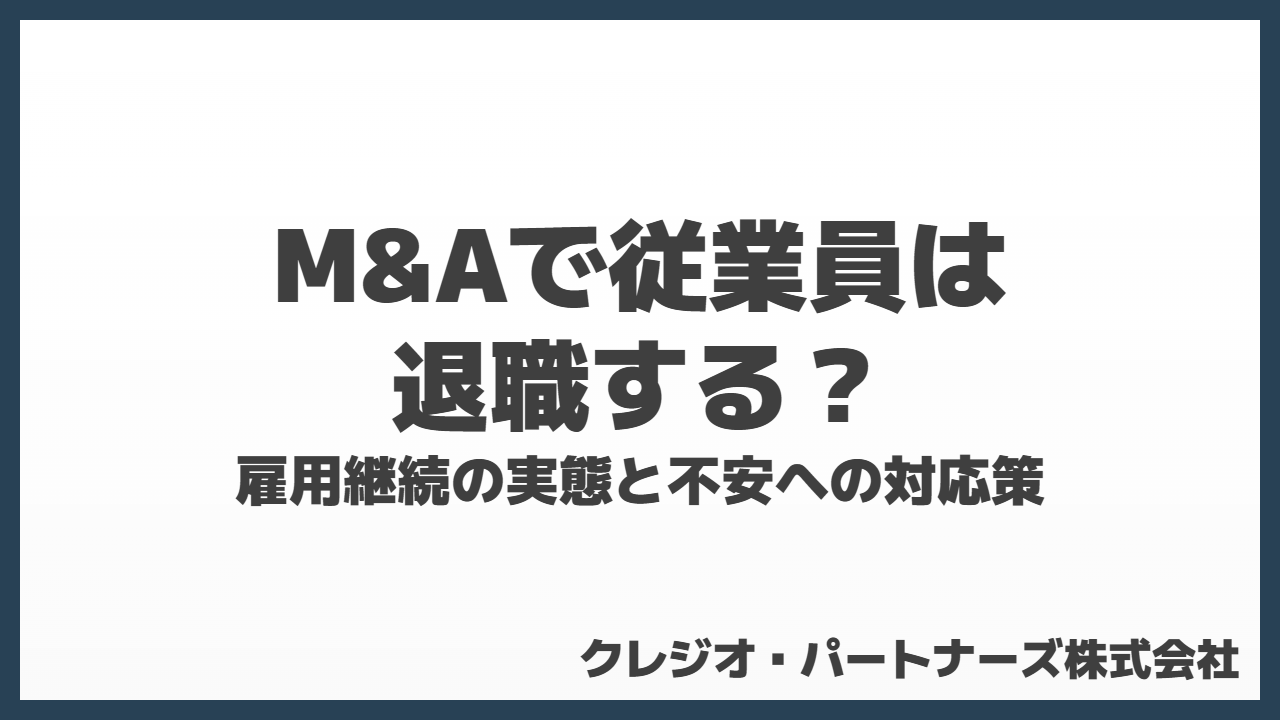M&A引継ぎ期間の目安|短期・長期パターンと経営者が注意すべき点

M&Aによる会社売却を検討するとき、多くの経営者が気にするのが「M&A後、経営者はいつまで会社に残る必要があるのか?」という点です。
実際の事例では6か月〜2年程度が平均的な引継ぎ期間ですが、1か月で退任するケースもあれば、3〜5年関与を続ける場合もあります。
本記事では、売手経営者・買手企業それぞれの希望や理由を整理し、引継ぎ期間を決める際の調整ポイントや注意点を解説します。
目次
記事のポイント
- M&A後の引継ぎ期間は「短期」「長期」「どちらでも可」の3パターン
- 売手経営者と買手企業では希望の理由が異なるため、調整が不可欠
- 「同業M&A」か「異業種M&A」かによっても希望期間は変わりやすい
M&A後の引継ぎ期間の平均・相場はどのくらい?
当社の過去の事例では、6ヶ月~2年がボリュームゾーンです。
中には1ヶ月で退任することもありますし、M&A後も3年や5年残るというケースもあります。また、売手経営者が元気で意欲があるうちはいつまででもというケースもあり、状況に応じて様々です。
実際には、売手経営者の現在の業務内容、引継ぎに必要な期間、ご意向と、買手経営者の意向によって、その引継ぎ期間は決まっていきます。
引き継ぎ期間でお悩みの方は、ぜひ一度クレジオ・パートナーズへご相談ください。
売手経営者が希望する引継ぎ期間のパターン
一般的に売手経営者が希望する引継ぎ期間は、大きく「なるべく早く」「少なくとも2~3年」「どちらでもよい(相手との協議次第)」の3つのパターンに分けられます。
3〜6か月で退任したい「短期型」
「3~6ヶ月の短期間で引継ぎをして、なるべく早く引退したい。」と思われるケースです。
自社株式を売却する以上はスパッと退きたいと思われる方や、株式売却の理由の中に「配偶者の介護が必要」、「自身の体調が悪い」等の急を要する理由がある場合、なるべく早いタイミングを希望されます。
2〜3年以上残りたい「長期型」
M&A後も少なくとも2~3年かけて、じっくりと引継ぎを終えたいと考えるケースです。
その理由としては、現時点で営業を売手経営者一人が担っており、取引先との人間関係が事業上重要であり、人間関係の引継ぎに2~3年かかる場合や、現場仕事は好きだし体力・気力もあるのでまだ仕事を続けたい等、比較的売手経営者の経営意欲が継続している場合が多いです。
逆に、M&Aにより、経営者という肩の荷がおりることで、グループ傘下の成長に意欲的になる経営者もいらっしゃいます。
相手次第で柔軟に決めたい「協議型」
引継ぎ期間にこだわりがない、又は、相手先の意向に沿いたい、というケースです。この場合、買手経営陣との協議により、その引継ぎ期間を決定することが多いです。
買手企業が求める引継ぎ期間の考え方
一般的に買手企業が売手経営者に求める引継ぎ期間の希望は、同じく「なるべく早く」「少なくとも2~3年」「どちらでもよい(相手との協議次第)」の3つのパターンに分けられます。
ただし、その理由については視点が異なります。
3〜6か月で交代してほしい「短期型」
引継ぎ期間を短くし、3~6ヶ月の短期間で引継ぎをして、売手企業の経営者にはなるべく早く引退してもらいたいと考えるケースです。
その理由として、売手経営者が長くいると売手企業の従業員がやりづらい=前社長と新社長のどちらの言うことを聞けば良いかわからなくなる、と言った理由や、売手経営者が長くいると買手企業として経営改革や変革が実行しづらい等の理由となります。
このような意向は、以下の買手企業に多い傾向があります。
- 過去のM&A後の経営経験(PMI経験)で、やりづらさを経験した
- 改革志向
- 経営再建が得意
- 業界再編盛んな業種(スケールメリット追求のために、オペレーションやフォーマットの統合が必要な業種。調剤薬局、小売など。)
2〜3年以上残ってほしい「長期型」
M&Aを行った後も、少なくとも2~3年は残って、じっくり引継ぎや経営協力をして欲しいと考えるケースです。
その理由として、売手経営者の人脈・技術・マネジメント・ノウハウを評価し、M&A後も必要としているため、上記のような引継ぎを希望するケースがあります。
このような意向は、以下の買手企業に多い傾向があります。
- 異業種である(ノウハウがないから不安)
- 寛容、柔軟
- 60歳超のシニア人材を重宝している(定年が実質ないなど)
双方で調整して決める「協議型」
売手経営者同様、買手企業にも引継ぎ期間にこだわりがないケースがあります。この場合も、双方の協議により、その引継ぎ期間を決定することが多いです。
自社に最適な引き継ぎ期間を知りたい場合は、当社までお気軽にお問い合わせください。
売手と買手の意向調整方法と合意に至るパターン
上記の売手の希望と買手の希望を組み合わせると、以下のマトリックスになります。わかりやすくするため上記のパターンを「短期」「長期」「どちらでも」に分けて整理します。
| 売手 | ||||
| 短期 | どちらでも | 長期 | ||
| 買手 | 短期 | 短期 | 短期 | 協議 |
| どちらでも | 短期 | 協議 | 長期 | |
| 長期 | 協議 | 長期 | 長期 | |
A群(水色)|双方が短期引継ぎを希望しスムーズに合意するケース
売手の希望と買手の希望が一致しているケースです。比較的スムーズに合意に至ります。
B群(緑)|短期希望×長期希望のズレを調整して合意するケース
一方が「どちらでも良い」で、一方が短期か長期かを明確に希望しているケースです。
こちらも比較的スムーズに合意に致ります。ただし、売手も買手も「どちらでも良い」が真意ではないことがあります。
特に売手経営者は、初めての経験のためイメージが湧かなかったり、決断できていなかったり、相手との相性で決めたい、というのが本音で、わからなくて「どちらでも良い」と言っている可能性もあります。
買手企業は、本当は早く退いてほしいが本音が言いづらくて「どちらでも良い」と言っていることもあります。M&A仲介会社は、その辺りの機微を見誤らずに、真意をしっかりと確認して掛け違えのないように注意をして進めることが重要です。
C群(黄色)|長期引継ぎを前提に段階的に権限移譲するケース
売手・買手ともに「どちらでも良い」のケースです。
一見調整が簡単に見えますが、M&A仲介会社としては慎重に対応しなければいけないケースです。売手・買手ともに真意を話していない、または、真意が定まっていない可能性があるため、双方の真意をしっかり確認してから調整を行うことが必要となります。
D群(赤色)|意向差が大きい場合の落としどころと注意点
売手・買手の意向が反するケースです。
売手経営者は、30年・40年経営してきた会社や業務の引継ぎに、相当な思いを持っておられます。買手企業も、リスクをとってM&Aを行う以上、「しっかり改革したい(だから早く引退して欲しい)」、「しっかり引継ぎして欲しい」という強い思いを持っています。
これらは売買価格と同じぐらい重要な条件であることもあり、価格で合意できてもこの部分で合意できないということもあります。売手経営者が短期で引継ぎ引退する場合であっても、買手には最後まで売手社長に対する敬意、気遣いを忘れないことで交渉・調整がスムーズに進みます。
敬意・配慮を欠いた対応・姿勢はM&Aのブレイク要因になりますし、M&A後のトラブルの要因になります。
売手経営者へのアドバイス|引継ぎ期間を決めるポイント
M&A後の引継ぎや、その後の関与期間は、まず売手経営者から希望を伝えるのが一般的ですし、その方が良いです。その理由は、買手企業の中には、「売手経営者の意向を尊重したい」と考えている企業が多いからです。
筆者の主観・経験則上の話となりますが、買手企業の意向は、同業又は異業種をM&Aで取得するケースで言うと、以下のような傾向だと思います。
買手企業の意向をどう捉えるべきか|引継ぎ期間で重視される要素
※事業承継型M&A(売手オーナー高齢、100%株式譲渡の場合)
| 同業 | 異業種 | |
|---|---|---|
| 短期で引退してほしい | 多い | 少ない |
| どちらでも良い | 中 | 中 |
| 長期間しっかり引継いでほしい | 少ない | 多い |
売手経営者の中には「経験したことがないからわからない」「相手に会ってみないとわからない」と考える方もいますが、そういった場合は、その思いや悩みをストレートにM&A仲介会社に伝える方が良いです。
M&A仲介会社は、疑問に答えてくれますし、そのような売手経営者の気持ちを踏まえて、相手先を探して調整してくれるはずです。
M&A引継ぎ期間のまとめ
今回はM&A後の引継ぎ期間をテーマに売手経営者・買手企業それぞれの立場での考えやニーズと、それを踏まえた上での売手経営者へのアドバイスをお伝えしました。
短期的・長期的・どちらでもよいというパターンに分けることはできますが、それでもケースバイケースになりますので、それぞれの意向を尊重し、交渉・調整が必要になります。
ただ、それでも同業か非同業かでその意向は左右されやすく、M&A後のビジネスを円滑に展開していくための視点も必要となります。売手経営者・買手企業の双方がそれぞれの意図を理解して、進んでいくことが重要であり、上手にM&A仲介会社等を利用して交渉・調整を進めて欲しいと思います。
クレジオ・パートナーズ株式会社広島を拠点に、中国・四国地方を中心とした地域企業のM&A・事業承継を専門に支援しています。資本政策や企業再編のアドバイザリーにも強みを持ち、地域金融機関や専門家と連携しながら、中小企業の持続的な成長と後継者募集をサポート。補助金や制度活用の知見を活かし、経営者に寄り添った実務的な支援を提供しています。
URL :https://cregio.jp/
M&A・事業承継について、
お気軽にご相談ください。