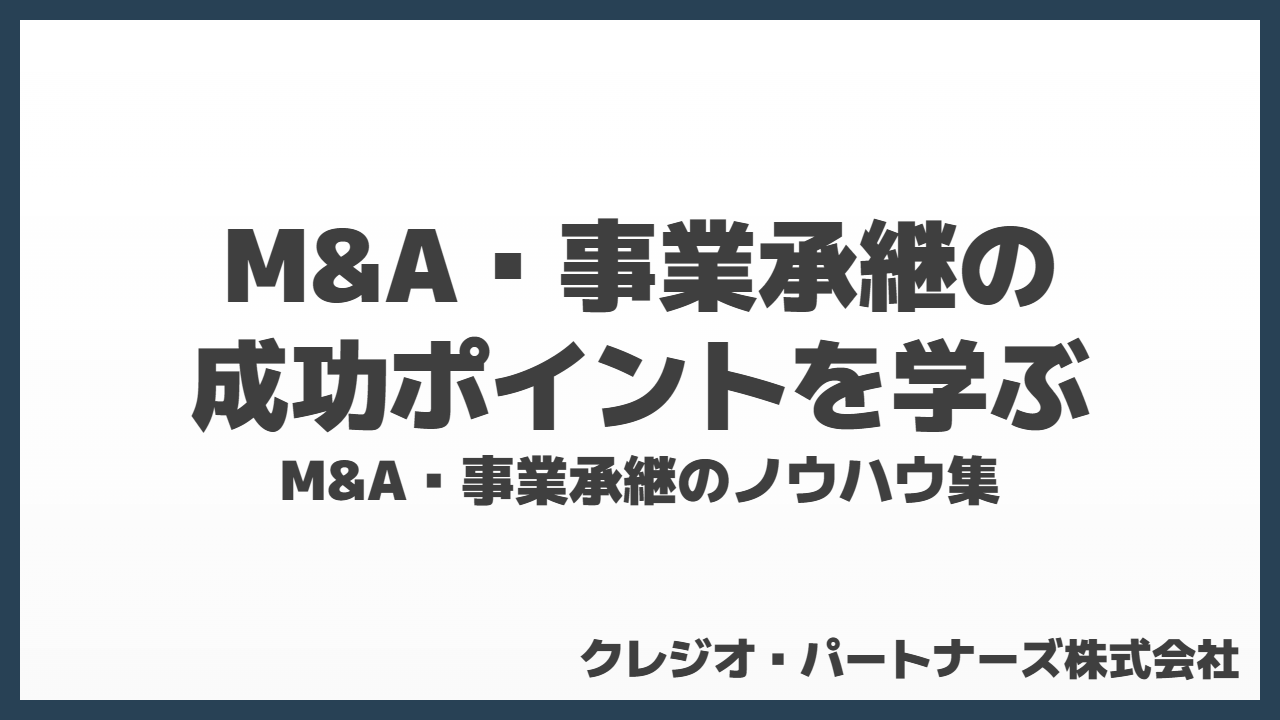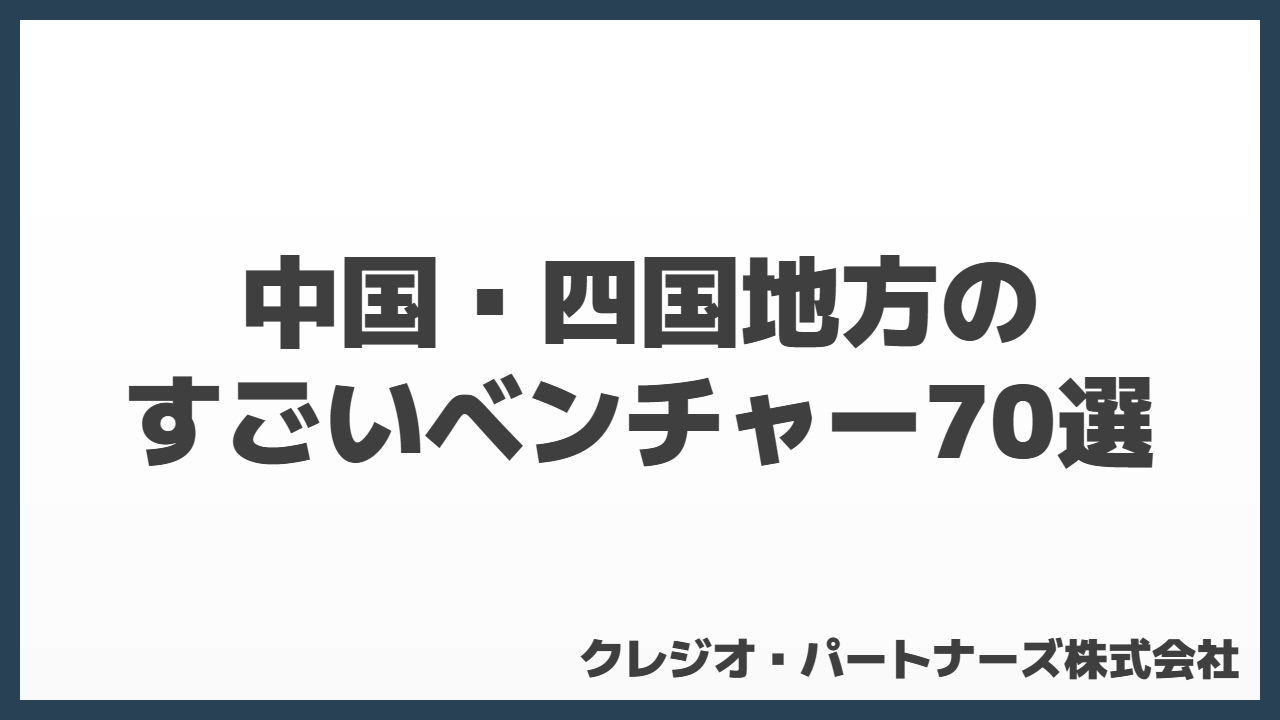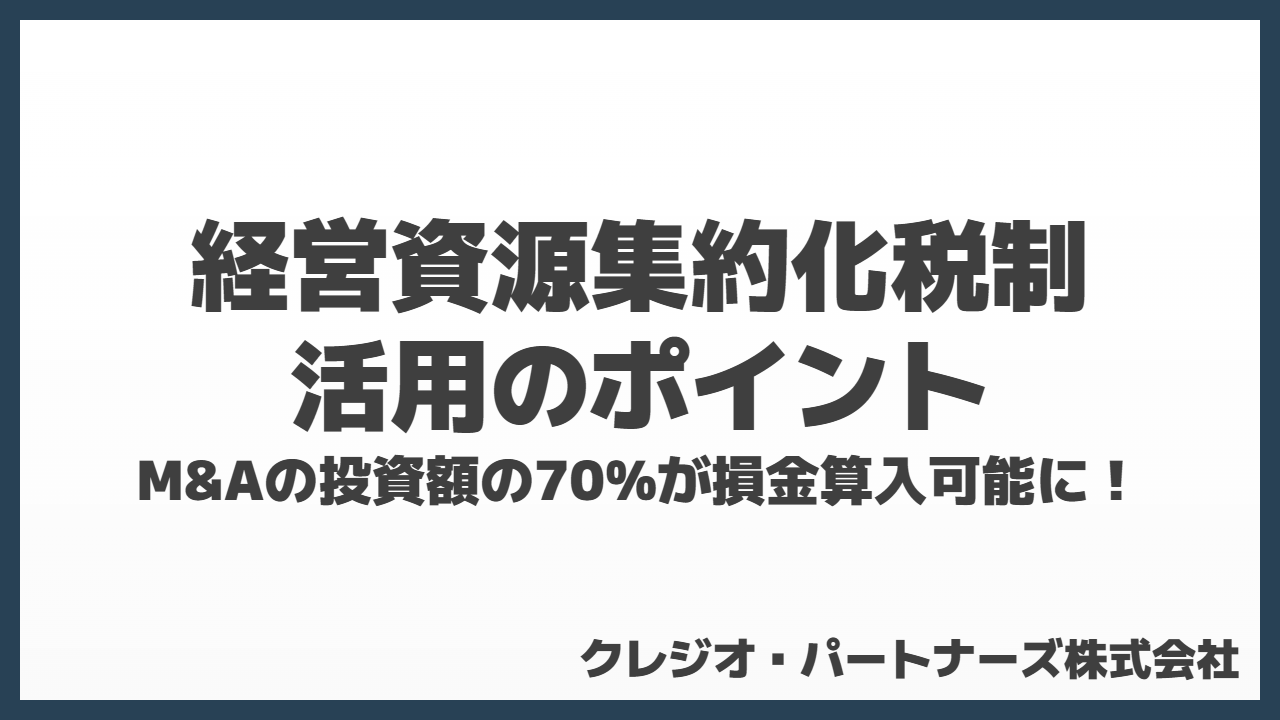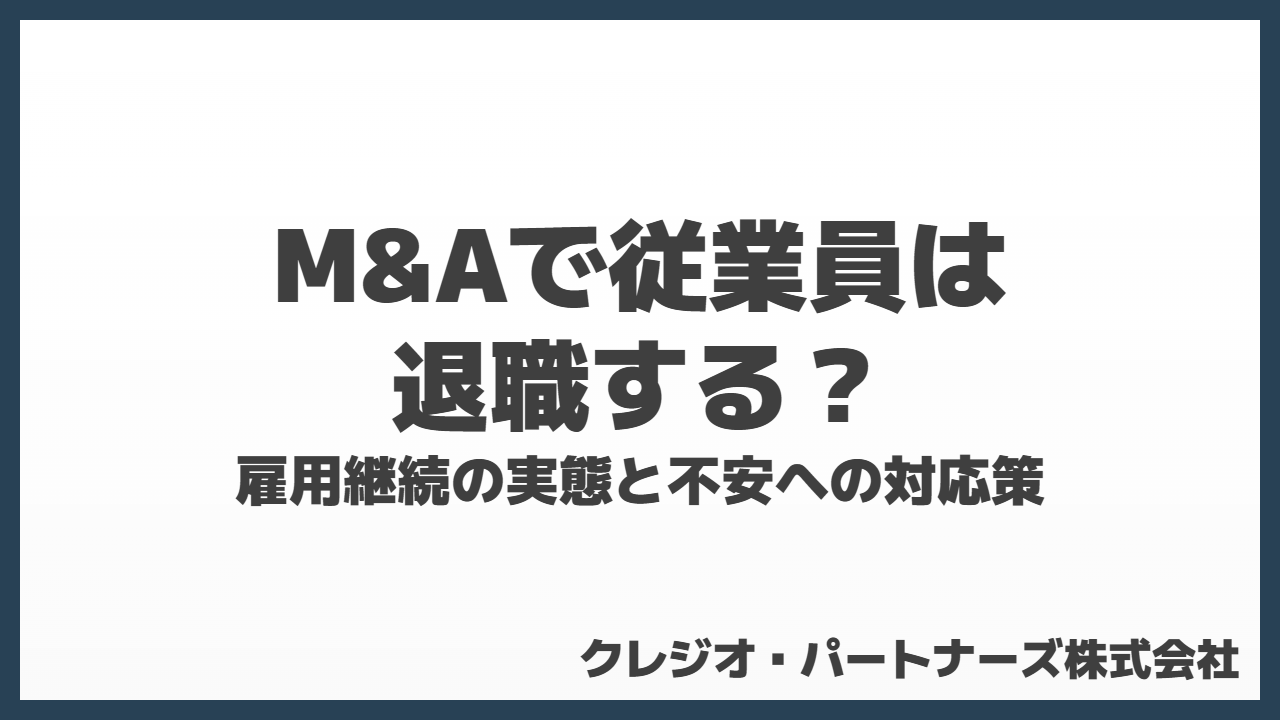会社を売却するなら同業?非同業?メリット・デメリットを徹底解説
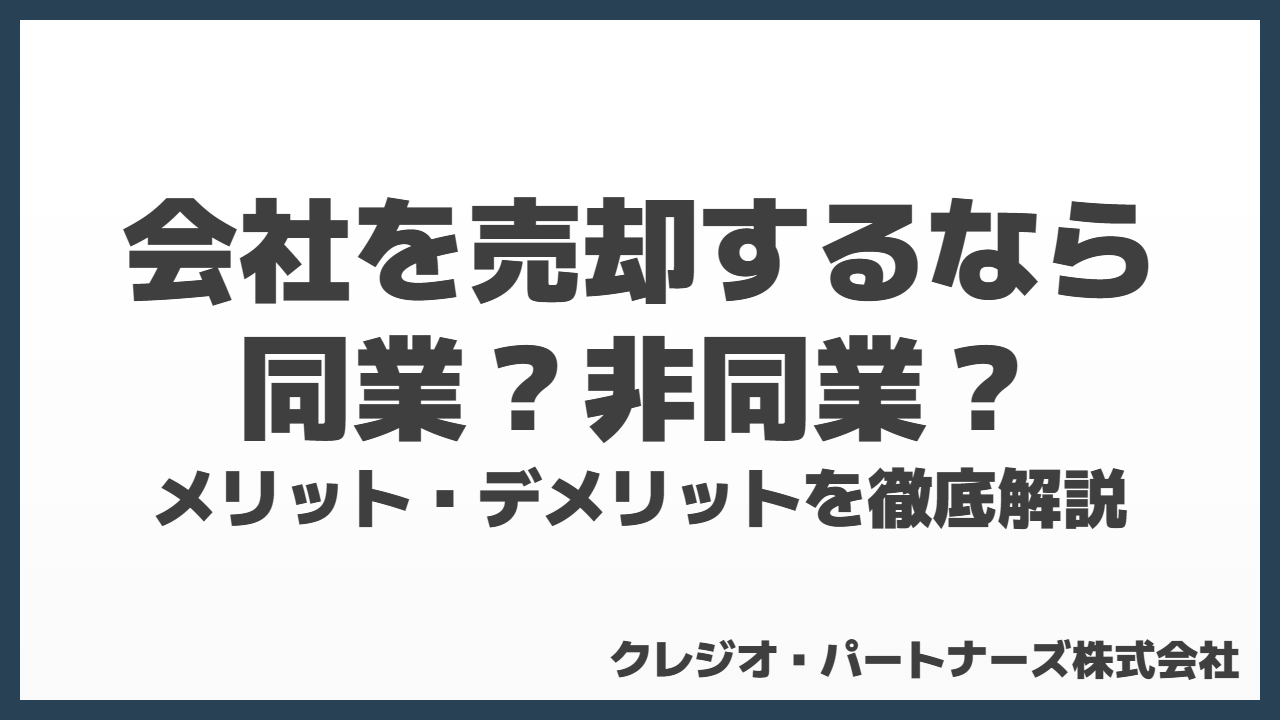
会社を売却・承継する際、経営者が必ず直面するのが「同業に譲渡すべきか、それとも非同業に譲渡すべきか」という選択です。
M&Aにおいて買い手は大きく①同業、②非同業、③ファンドの3つに分けられ、それぞれ期待できるシナジー効果や譲渡後の経営環境は大きく異なります。複数の候補先が現れた場合、自社にとってどのパートナーが最も適しているのかを判断することは簡単ではありません。
本記事では、売り手企業の視点から「同業」と「非同業」に譲渡する場合のメリット・デメリットを整理し、後悔しないM&Aの意思決定に役立つポイントを解説します。
目次
会社売却で迷いやすい同業と非同業の違いとは?
会社売却(M&A)を検討する際、オーナー経営者が最も悩むポイントの一つが「同業に売却すべきか、非同業に売却すべきか」という選択です。どちらの選択肢にもメリット・デメリットがあり、譲渡後の事業の成長、社員の雇用維持、社風の継続性などに大きな影響を与えます。
一般的に同業への売却は、事業理解の速さやスケールメリットが得られる一方で、買い手の経営色が強く反映されやすいという特徴があります。一方、非同業への売却は、売り手企業の文化や社風が尊重されやすい半面、後任経営者を派遣してもらえないなど、承継体制に課題が生じるケースもあります。
このように、同業・非同業の違いは単なる「業種」の違いだけでなく、譲渡後の会社のあり方を左右する大きな判断要素となります。まずは、この2つの違いを正しく理解し、どちらが自社に合うかを見極めることが、失敗しない会社売却の第一歩となります。
会社売却における買い手の種類と特徴
会社売却(M&A)における買い手は、大きく 「同業」「非同業」「ファンド」 の3つに分類されます。
どの買い手を選ぶかによって、譲渡後の事業運営、社員の働き方、企業文化の維持、成長戦略の方向性が大きく変わるため、買い手の特徴を理解しておくことは極めて重要です。以下では、それぞれの買い手が持つ特徴をコンパクトに整理します。
同業の特徴
同業への売却とは、売り手企業と同一もしくは近い事業領域を持つ企業への譲渡を指します。同業の買い手は売り手事業に対する理解が深く、既存事業との統合(バリューチェーン統合・顧客共有・人材配置など)を通じてシナジーを生みやすい点が特徴です。
- 業界知識・オペレーションへの理解が速い
- 営業・仕入れ・物流などが統合しやすい
- スケールを活かした成長戦略と効率化が図られやすい
競争環境が激しい業界ほど、同業間でのM&Aが活発に行われる傾向があります。
非同業の特徴
非同業への売却とは、売り手企業とは異なる業界の企業への譲渡を指します。完全に異業種というよりも、周辺・隣接分野やサプライチェーンが異なる企業が買い手となるケースが多く、既存事業の独自性が尊重されやすい傾向があります。
- 経営理念や文化が維持されやすい
- 異なる顧客基盤や販路との掛け合わせによる新しい展開が可能
- 事業の自主性・ブランドが残りやすい
事業の独自性を残したいという企業が選択することが多い買い手分類です。
ファンドの特徴
ファンド(PEファンド・投資ファンド)は、企業の株式を取得し、一定期間、経営改善・成長支援を行ったうえで売却(エグジット)することを目的とする投資主体です。事業承継問題の解決手段として存在感が高まっており、専門知識や経営管理体制の強化を期待できる買い手類型です。
- 後継者不在企業の承継先として活用されやすい
- 財務・管理・組織のプロによる経営支援が得られる
- 成長投資(設備投資・採用・新規事業)が進みやすい
同業・非同業とは異なり、「成長」「ガバナンス強化」を軸に企業価値向上を支援する点が特徴です。
同業へ譲渡する場合のメリット・デメリット
同業企業への譲渡は、M&Aにおいて最も一般的なケースの一つです。
特に調剤薬局、医療機器卸、食品卸・小売、運送業といった業種では、同業同士の統合によるスケールメリット(同じ種類の事業をまとめることで単体以上の効果を発揮すること)が大きく、業界再編の動きが活発化しています。
現場感覚としても、こうした業界では「後継者問題を解決するための事業承継」よりも、「大手企業との統合による効率化やシェア拡大」を目的に同業へ譲渡されるケースが多く見られます。
同業へ譲渡するメリット
- スケールメリットを獲得でき、競争力や収益性が高まりやすい
- 買い手が業界事情に精通しているため、事業理解が早い
- 後任経営者として、業界経験や経営経験のある人材を派遣してもらいやすい
同業へ譲渡するデメリット
- 買い手企業の経営理念や社風が強く反映されやすく、売り手企業の文化や商売スタンスが維持されにくい場合がある
非同業へ譲渡する場合のメリット・デメリット
非同業へ譲渡する場合は、以下のようなメリット・デメリットが挙げられます。
非同業へ譲渡するメリット
特に大きいと考えられるメリットは「売り手企業の経営理念、社風、商売スタンス等や自主性が尊重されやすい」点です。買い手は、売り手事業の経営経験がないため、売り手の経営理念や商売スタンス等が継続されるケースが多いです。
- 売り手企業No.2である専務への株式承継(MBO)までは難しいが、専務に経営能力がありM&A後も十分に経営を任せられるし任せて欲しい。
- 売り手の強みが独自の経営理念、社風、商売スタンスであり、M&A後もこれを継続して欲しい。
上記のようなケースは、相手先は非同業の方が適切なこともあります。
非同業へ譲渡するデメリット
一方で、非同業のM&Aでは、後任経営者(業界経験、経営経験のある人材)を派遣してもらえない可能性もあります。
- ① 任せっぱなしにされることがある
- ② 後任経営者を出してもらえないことがある
- ③ スケールメリットを得にくい
売り手企業の社内に後継経営者として適切な人材がおらず、後継社長を買い手企業から派遣してもらいたいという場合には、その旨をしっかり伝えた上で、買い手企業と認識のズレがないようにする必要があります。
ファンドへ譲渡する場合のメリット・デメリット
ファンド(投資ファンド・PEファンド)への譲渡は、同業・非同業とは異なる選択肢として、近年の中小企業M&Aで存在感を高めています。ファンドは企業の株式を取得したうえで、一定期間、経営チームとともに成長戦略を描き、最終的に株式売却(エグジット)を行う投資モデルが特徴です。
「後継者不在問題の解消」「成長投資のサポート」「ガバナンス体制の強化」など、ファンド独自の役割が期待される一方、投資回収を前提とした経営管理が求められるため、事業の安定性を重視したいオーナーにとっては慎重に検討すべき側面もあります。
以下では、ファンドへ会社を譲渡する場合のメリット・デメリットを整理します。
ファンドへ譲渡するメリット
① 専門的な経営支援を受けられる
ファンドには、財務、経営管理、人材組織、マーケティングなどの専門家が在籍しており、企業価値向上を目的とした実務的な支援を受けられます。特に管理体制が弱い中小企業では、ガバナンス整備・数字管理・採用強化などが進むことで、企業の基盤が大きく改善されるケースも多くあります。
② 後継者不在でも承継できる
ファンドは経営者の退任を前提に投資することも多いため、社内に後継者がいなくても承継が可能です。外部から後任社長を招聘したり、ファンド側と連携して経営チームを組成したりするなど、他の買い手にはない柔軟な体制構築ができます。
③ 事業の独立性を保ちやすい
同業や非同業の企業に譲渡する場合と異なり、ファンドは既存の事業を吸収・統合するのではなく、「単体事業として成長させること」に価値を置きます。そのため、社名・ブランド・事業構造が維持されやすく、社員の働き方が大きく変わりにくい点もメリットです。
④ 新たな成長投資を行いやすい
設備投資、採用、人材強化、新規事業、システム導入など、オーナー時代にはできなかった投資がしやすくなります。「会社をもっと大きくしたいが、自分の代ではリスクを取りにくい」と悩む経営者にとって、ファンドは力強いパートナーになります。
ファンドへ譲渡するデメリット
① 一定期間内に成果が求められる
ファンドは投資家から預かった資金を運用する立場であるため、企業価値を高めたうえでエグジット(売却)を目指します。そのため、経営にはKPI管理やスピード感が求められ、これまでの「家業的な経営」とは異なる運営スタイルになる場合があります。
② 事業売却(再M&A)が前提である
ファンドは永久保有ではないため、5〜7年程度で次の買い手に引き継ぐ(再M&A)ことが一般的です。従業員の不安を軽減するためには、初回M&A時に「その後の方針」をファンド側と丁寧に擦り合わせておく必要があります。
③ 経営陣に一定の負荷がかかる可能性
数字管理や報告体制の強化が進むため、経営陣には従来以上のガバナンスが求められます。特に、中小企業で「属人的な管理」に慣れている組織は、ルールづくりや仕組み化に一定の負荷を感じることもあります。
④ 経営者の残留を求められる場合がある
「引退したくて売却したい」場合でも、一定期間の残留を求められるケースがあります。この点はファンドによって異なるため、交渉段階で慎重に確認が必要です。
どの買い手が自社に合う?判断するための3つの視点
会社売却や事業承継において、同業・非同業・ファンドのどれが最適な買い手となるのかは、企業ごとに大きく異なります。
M&Aにおける「買い手の選び方」は、譲渡後の事業の成長、社員の雇用、文化の維持など、多方面に影響する重要な意思決定です。ここでは、どの買い手が自社に合うかを判断するための3つの視点を整理し、オーナー経営者が後悔しない選択をするための考え方を解説します。
自社の強み(文化 or 仕組み)をどこに置くか
最初の判断軸は、「自社の価値(強み)がどこにあるのか」です。企業によって、強みが 文化・理念・人材 にあるのか、あるいは 仕組み・ノウハウ・事業モデル にあるのかで、最適な買い手は変わります。
●文化・理念・社風が強みの場合
- 社員の定着率が高い
- お客様との関係構築が強い
- 独自の商売スタンスが評価されている
このような企業は、非同業 or ファンドの方が相性が良い傾向があります。同業に譲渡すると文化が吸収され、独自性が失われる可能性があるためです。
●仕組み・効率性・事業モデルが強みの場合
- 標準化されたオペレーション
- 仕組み化された営業プロセス
- 事業モデルの再現性が高い
こうした企業は、同業への譲渡が極めて相性が良く、スケールメリットを最大化しやすくなります。
後継者候補が社内にいるかどうか
次に重要なのは、社内に後継者候補がいるかどうかです。これは、会社売却の方向性を大きく左右する最大級の判断基準です。
●後継者候補が社内に「いる」場合
たとえば専務・部長クラスが経営センスを持ち、「M&A後も会社を引っ張れる」と判断できる場合は、非同業 or ファンドでも十分に承継が成立します。
特に非同業の場合、「経営は売り手の内部人材に任せる」ケースが多く、社内後継者にとってチャンスが広がります。
●後継者候補が社内に「いない」場合
- 親族に継ぐ人がいない
- 役員や幹部に経営を任せられない
- 組織にマネジメントの経験者が不足している
この場合は、後任経営者を派遣できる 同業 or ファンドが候補になります。特にファンドは、外部からプロ経営者を招聘する体制を持っているため、「完全に後継者不在」の企業にとって有力な選択肢です。
譲渡後に何を最優先したいか(自主性・成長・安定など)
最後の判断軸は、オーナーが譲渡後に何を最優先したいかです。会社売却の目的によって、選ぶべき買い手は変わります。
●自主性・社風の維持を最優先する場合
→ 非同業 or ファンド
- 組織文化を尊重しやすい
- 社名やブランドを維持しやすい
- 社内人材が引き続き活躍しやすい
「会社のカラーを残したい」企業に適しています。
●短期間での成長や事業拡大を優先する場合
→ 同業
- スケールメリットで収益が改善
- 業務統合で効率化が進む
- 営業・物流・仕入れなどが強化される
特に調剤薬局・運送・食品卸などは同業譲渡で効果が出やすい業種です。
●ガバナンス強化や第二創業を目指す場合
→ ファンド
- 専門家による成長支援
- 財務管理や組織づくりが一気に進む
- 成長投資を積極的に実行できる
「この会社をもう一段強くしたい」という場合に向いています。
まとめ
今回は買い手企業が同業・非同業だった場合に分けて、そのメリット・デメリットを整理しました。
買い手企業のニーズが様々であるように、売り手企業のニーズも、単純に後継者がいないという課題だけでなく、社員の雇用継続や事業の独自性維持など、多面的な経営課題と結びついています。そのため、どの企業に事業を引き継いでもらうかの判断は、オーナー経営者にとって非常に難しいテーマです。
ただでさえ日々多忙な経営者が一人で悩み続けるのは現実的ではありません。俯瞰的な視点を持つ専門家やM&A仲介会社に早めに相談することで、候補先の幅広い可能性や過去の成功事例を参考にしながら、自社に合った最適な選択肢を見つけることができます。
後悔しない会社売却・事業承継のために、まずは信頼できる相談先に一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。
- 買い手が同業:CASE04:広島県の社会福祉法人が実現した介護・福祉施設「たかやの郷」の事業譲渡
- 買い手が非同業:CASE02:不動産・フード・福祉の多角化を加速|みどりホールディングスのM&A活用事例
クレジオ・パートナーズ株式会社広島を拠点に、中国・四国地方を中心とした地域企業のM&A・事業承継を専門に支援しています。資本政策や企業再編のアドバイザリーにも強みを持ち、地域金融機関や専門家と連携しながら、中小企業の持続的な成長と後継者募集をサポート。補助金や制度活用の知見を活かし、経営者に寄り添った実務的な支援を提供しています。
URL:https://cregio.jp/
M&A・事業承継について、
お気軽にご相談ください。